運送業に関連する主な法律は?輸送の安全のための改正点なども紹介
- 物流
「トラック運転手が働くうえで、知っておくべき法律はある?」
「今の自分の労働時間と休憩時間の取り方は法的にOK?」
「労働基準法の違反を問いたいときは、どうすれば良い?」
このようにトラック運転手の中には、自分の労働状況がこれで良いのか知りたい人や、今後改善できるよう、どうにかしたいと考えている人もいるでしょう。
この記事では、運送業に関連する主な法律を紹介します。そのうえで、自動車運転者の労働時間の改善基準について解説するため、この記事を読むことで法律上どのように労働条件が定められているか分かるでしょう。
この記事を参考に法律に関する理解を深め、現在の自分の労働状況について検証したり、改善できるよう働きかけたりしてみてください。
運送業の種類

「貨物自動車運送事業法」によると、「貨物自動車運送事業」とは「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」の3種類と定義されています。
運送業は有償で貨物を運送する事業です。「一般貨物自動車運送事業」は軽自動車や二輪自動車を除く自動車を、「貨物軽自動車運送事業」は軽自動車や二輪自動車を使用します。
また、「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の人の需要に対して有償で自動車を使用して貨物を運送する事業を指します。
出典:貨物自動車運送事業法|e-Gov 法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000083
運送業に関連する主な法律

運送業に関連する主な法律は、「貨物自動車運送事業法」や「道路運送車両法」、「道路交通法」です。
運送業に携わる者は、これらの法律に関する知識を頭に入れておくと良いでしょう。
出典:貨物自動車運送事業法|e-Gov 法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000083
出典:道路運送車両法|e-Gov 法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000185
出典:道路交通法|e-Gov 法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
| 法律名 | 政令・府令・省令 |
|---|---|
| 貨物自動車運送事業法 | 貨物自動車運送事業法施行規則(省令) |
| 貨物自動車運送事業法 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則(省令) |
| 道路運送車両法 | 道路運送車両法施行令(政令) |
| 道路運送車両法 | 道路運送車両法施行規則(省令) |
| 道路交通法 | 道路交通法施行令(政令) |
| 道路交通法 | 道路交通法施行規則(府令) |
| 労働基準法 | 労働基準法施行規則(省令) |
輸送の安全のための貨物自動車運送法の改正

平成30年に、より安全な運送のために「貨物自動車運送事業法」が改正されました。これにより、事業者が遵守すべき事項として、「事業用自動車の定期点な点検・整備の実施」などの改正・追加がありました。
出典:貨物自動車運送事業輸送安全規則|e-Gov 法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402M50000800022
出典:貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律について|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000084.html
労働時間通算と労働者災害保険法の改正

令和2年に「労働者災害補償保険法」が改正され、複数の会社で働く人はその制度改正の対象となる可能性があります。事業主が異なる複数の事業場で労働する場合、労働基準法第38条の運用によって労働時間が通算されます。
そして、雇用されているすべての会社における仕事の負荷を総合的に評価して、労災認定されます。
出典:労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html
出典:副業・兼業の促進に関するガイドライン|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf
出典:労働基準法 第38条|e-Gov 法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
労働基準法・改善基準告示の6つのポイント
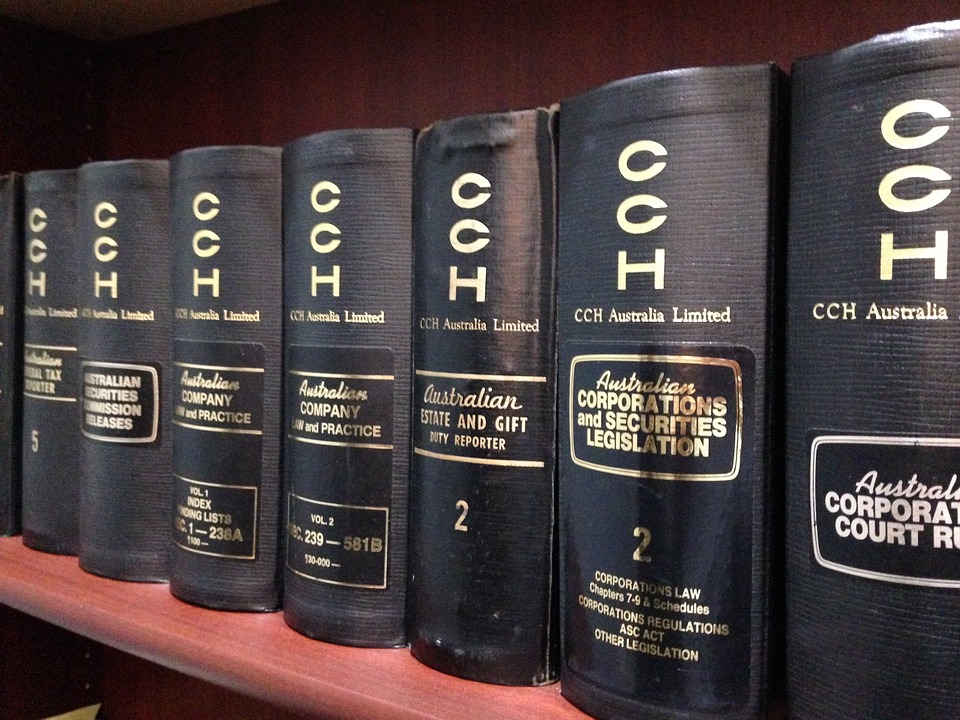
令和2年度「過労死等の労災補償状況」について、脳・心臓疾患の労災請求件数および支給決定件数は、ともに道路貨物運送業がもっとも多くなっています。このような背景から、運送業の運転手に対して働き方の改革が求められています。
トラック運転手に対して策定された、いわゆる「改善基準告示」について見ていきましょう。
出典:改善基準告示の見直しについて(参考資料)|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000849038.pdf
- 改善基準告示
- 自動車運転者の拘束時間は基本1日13時間まで
- 手待ち時間(荷待ち時間)も労働時間
- 休息期間は原則継続する8時間以上が必要
- 運転時間は継続で4時間などの制限がある
- 休日は32時間を下回ってはならない
改善基準告示
平成元年、自動車運転者の労働条件の改善を図るため、厚生労働大臣告示である「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」が策定されました。
「改善基準告示」は、トラック運転者を含む自動車運転者の、主に労働時間に関する基準に関して言及されています。
出典:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73028500&dataType=0&pageNo=1
自動車運転者の拘束時間は基本1日13時間まで
改正基準告示では、自動車運転者の拘束時間は1日13時間以内が基本とされています。また、延長する場合も、上限となる拘束時間は16時間です。
なお、拘束時間とは始業時刻から就業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間の合計時間のことです。
出典:改善基準のポイント|厚生労働省労働基準局
参照:https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000016434.pdf
手待ち時間(荷待ち時間)も労働時間
手待ち時間(荷待ち時間)は、運転時間や自動車の整備、荷扱いなどの作業時間と同じく、労働時間に含まれています。その労働時間と休憩時間を足したものが拘束時間となっています。
出典:改善基準のポイント|厚生労働省
参照:https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000016434.pdf
休息期間は原則継続する8時間以上が必要
1日の休息期間は、勤務終了後、原則継続する8時間以上であることが必要です。
休息期間とは勤務と次の勤務の間の時間であり、労働者にとって自由な時間を指します。つまり、勤務と勤務の間が8時間以上空いていなければならないということになります。
出典:改善基準のポイント|厚生労働省
参照:https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000016434.pdf
運転時間は継続で4時間などの制限がある
1日の運転時間は2日(48時間)の平均で9時間、1週間の運転時間は2週間ごとの平均で44時間、という上限が設けられています。
連続運転時間は4時間が限度で、運転開始後4時間以内または4時間経過直後に休憩時間を30分以上確保する必要があります。また、休憩時間を1回10分以上にすることで分割することもできるため、自分に合った休憩の取り方をしましょう。
出典:改善基準のポイント|厚生労働省
参照:https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000016434.pdf
休日は32時間を下回ってはならない
休日とは「休息期間+24時間」の連続した時間のことを指します。前述したとおり、休息期間は原則として8時間以上確保されなければいけないため、休日は32時間以上の連続した時間ということになります。
なお、改善基準告示では、いかなる場合でもこの休日が30時間を下回ってはいけないと定められています。
出典:改善基準のポイント|厚生労働省
参照:https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000016434.pdf
労働基準法違反を問えそうな場合の確認ポイント

前述したとおり、令和2年度において脳・心臓疾患の労災件数は道路貨物運送業がもっとも多い状況です。トラック運転手として働いていると、勤務している会社によっては厳しい勤務状況に陥る場合もあるでしょう。
労働基準法違反を問えそうな場合に、確認しておくべきポイントを解説します。
出典:改善基準告示の見直しについて(参考資料)|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000849038.pdf
36条協定がない場合の残業代未払いの有無
いわゆる「36協定(サブロク協定)」とは、労働基準法第36条に定められている労使協定のことです。そこには、労働者または労働組合との協定で定めるとおりに労働時間を延長し、休日労働させられることが明文化されています。
その36協定を締結していない、もしくは36協定を締結していても労働基準監督署に届け出ていないのに時間外労働をさせた場合、その会社は法律違反となります。
さらに、労働基準法第37条より、時間外または休日・深夜の労働には割増賃金を支払わなければいけません。そのため、36協定の有無、残業代未払いの有無を必ず確認しましょう。
出典:労働基準法|e-Gov 法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
長時間労働の記録
前述したとおり、トラック運転手の拘束時間や労働時間、運転時間、休息期間には明確に上限が決められています。そのため、労働基準法違反を問うためには、タイムカードや勤務時間記録、運転記録などが必要になります。
それらが得られない場合は、労働時間や運転時間、休日・休暇、休憩時間の記録を取っておきましょう。そして、万が一労働基準法違反を問いたい状況が訪れた場合は、この記録を活用します。
パワハラの証拠収集
2020年に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)」が改正され、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました。
この法律により、パワーハラスメント(パワハラ)に対する事業主・労働者の責務が法律上明確化されています。
パワハラの解消に向けては自治体の労働局に相談しますが、その際パワハラの証拠となる音源や記録を収集しておくと役に立ちます。ただし、個人的なトラブルとして受け取られる可能性もあるため、労働局での対応が難しい状況の場合は弁護士に相談しましょう。
出典:職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000683138.pdf
運送業者関係の法律はしっかり確認しておこう

他の分野同様、物流業界も働き方改革が進み、労働環境が見直されつつあります。そのため、現在働いている勤務先よりも好条件の求人が見つかる可能性もあります。
現在の勤務体制や労働環境が良いか悪いかを判断するには、運送業界の現状を知ることが必要になるでしょう。そして、運送業に関係する法律について確認しておくことが大切です。最終的に、これらの法律に関する知識が自分自身を守ることにもなるでしょう。
