【2024年問題】荷主がやっておきたい対策とは?受ける影響や罰則内容を解説
- 物流
「2024年からトラックドライバーの時間外労働が制限されるけど、具体的に何が変わるの?」
「2024年問題で荷主はどんな影響を受けるの?」
「罰則は受けたくないから、事前にきちんと対策しておきたい!」
このように2024年の物流業界の変化について、きちんと理解しておきたいと考えている荷主の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、物流業界の2024年問題の概要、問題によって荷主が受ける影響を解説しつつ、その対策についてご紹介します。
この記事を参考にすることで、物流業界が今かかえている課題を理解し、荷主が打ち出すべき解決策を確認できます。具体例を交えながらまとめていきますので、関係する部分から解決策が見つけられるでしょう。
2024年問題への対策をきちんと講じられるように、ぜひ最後まで記事をチェックしてみて下さい。
荷主も2024年問題の対策をする必要があるの?

2024年問題は、ドライバーの拘束時間や時間外労働の制限によって、引き起こされる問題の総称です。ドライバーの労働時間の減少は輸送にあたるリソースが低下してしまいますので、今までと同じように依頼するのが難しくなる可能性もあります。
物流業界として対策は必須ですが、運送を依頼する荷主にとっても対策が必須になる問題です。
物流の2024年問題とは

2024年4月から、トラックドライバーの時間外労働が年960時間(休日労働は含まない)までの上限規制がかかり、改正改善基準告示の適用によって、ドライバーの拘束時間が現状に比べ制限されます。
「2024年問題」とは、このまま対策を講じないまま、物流の停滞が引き起こされることの総称です。ドライバー1人あたりの輸送能力の低下や、ドライバーを担う人材不足は深刻な問題となっており、現在の社会において必要不可欠な物流業界の解決すべき課題となっています。
出典:3.自動車運送事業における時間外労働規制の見直し|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001620626.pdf
働き方改革関連法による労働条件の改善が目的
トラックドライバーは、全産業と比べても年間労働時間が長いのが現状です。一方で年間の所得額はやや低くなっており、こうした状況から物流業界の環境整備が必要とされていました。
そこで物流業界の環境整備の一環として、2024年4月より「時間外労働の上限規制」が適用されます。
働き方改革関連法は時間外労働の上限規制の他にも、有給休暇の取得義務化なども盛り込まれており、労働者の待遇改善が目的です。
また、トラックドライバーに対しては改善基準告示の改正によっても長時間労働を防ぐ試みがされており、改正によってドライバーが拘束される時間が減るでしょう。
出典:「働き方改革関連法」の概要|厚生労働省 愛知労働局
参照:https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_kintou/hatarakikata/newpage_01128.html
出典:トラック運転者の改善基準告示|厚生労働省
参照:https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice
【荷主が特に知るべき】荷主勧告制度
荷主勧告制度とは、トラックドライバーの法令違反があった際、荷主側の指示など主たる要因が荷主側に起因すると認められた場合、国土交通大臣によって勧告が行われることです。荷主勧告が発動した場合、荷主名や事案の概要が公表されます。
これは、違反となるような依頼をするのはもちろんですが、上記の時間外労働の上限を超えていた場合も働き方改革関連法違反です。
荷待ち時間の改善が見られなかった場合や非合理な到着時間の設定、やむを得ない遅延に対してのペナルティなども調査の対象となります。
出典:荷主勧告制度改正の概要|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/common/001024705.pdf
出典:荷主の皆様へ…|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/common/001204970.pdf
2024年問題による荷主が受ける影響

2024年問題によって、さまざまな影響が荷主に対してあると考えられます。ドライバーの労働時間が制限されると、輸送距離や運賃といった部分で制限が重くのしかかってくるでしょう。
また、現状で運用できているものが制限によって、うまく稼働しない可能性も考慮しなければなりません。対策を講じる前にどのような影響があるかを考えてみましょう。
委託の条件が厳しくなる
ドライバーの労働時間の短縮によって、現状の運送会社との条件が合わなくなるケースが考えられます。配送に必要な人員や費用面など、条件を見直す必要が出てくるでしょう。
条件が合わない場合は、別の取引先を開拓することも考えられます。しかし、業界全体が人員不足に陥っているため、需要に対して新たな取引先を開拓するのは難しいでしょう。
荷主は出荷時のスケジュールの見直しや委託先の開拓など、負担が大きくなることが考えられます。
輸送距離に制限がかかる
ドライバーの労働時間短縮は、1人当たりの運行時間の短縮に直結します。これまで1人で運送できていた距離が、2人あるいは2日かかってしまう可能性も考慮しなければなりません。
特に長距離輸送に関しては、これまでと同じような条件で、運送を依頼することが難しくなるでしょう。
運賃が上昇する
ドライバーの労働時間が減ることで、輸送能力が低下するため、運送会社の利益低下につながります。一回の輸送量が減れば、その分単価を上げるなどの対策が予想できるため、結果的に運賃の上昇が懸念されるでしょう。
また、中小企業の割増賃金率が2023年4月から大企業と同率に上がるなど、人件費の高騰も予想されます。人材不足が問題とされている中、企業の対応として給与の引き上げに伴う運賃の上昇も予想されるでしょう。
出典:中小企業の皆様へ|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
集荷時間の前倒しが増える
ドライバーの稼働時間に制限がかかると、集荷時間の前倒しなども増えるでしょう。ドライバーの荷待ち時間は、拘束時間の中でも特に課題とされている点です。
時間の短縮や積み荷の仕分けなどの工夫に対して、柔軟な対応が求められます。
荷主がやっておきたい2024年問題の対策

2024年問題は、荷主にとって、大きな課題となることが確認できます。では、この問題に対して、荷主側がとるべき対策は、どのようなものが考えられるでしょうか。
まず、ドライバーの待機時間を減らしたり、作業の効率化を促すことが考えられます。モーダルシフトの利用や、荷役の際にパレットを利用するなどの取り組みが必要です。
これらの対策には、運送業者と荷主の協力が大切です。対応策を理解し、これからの対策に生かしましょう。
モーダルシフトを利用する
モーダルシフトとは、長距離輸送においてトラックなどの自動車からフェリーや鉄道などへの利用に転換することです。
トラックドライバーは最寄りの港湾や駅までの輸送で済むので、拘束時間の短縮につながります。一方で、トラックなどと異なり、運行ダイヤが決められているので、出荷時間を厳守する必要があります。
また、物流における環境負荷の低減を進める上でも、大切な取り組みといえるでしょう。地球温暖化対策としても推奨されていることから、国土交通省でもモーダルシフト等推進事業として実施しています。
出典:モーダルシフト等推進事業|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/ms_subsidy.html
共同配送をする
トラックの積載効率を上げ、コストの削減を図るために荷主同士が連携して、配送業務を行う取り組みを共同配送といいます。
各荷主が共同倉庫に荷物を持ち寄り、そこから納品先へ一括で配送するので、トラックの数を削減、積載率の向上が見込めます。
輸送網を集約する
集荷や配送の際の効率化として、輸送網を集約することも大切です。集荷先や配送先が分散していると、それぞれに荷待ちや荷役時間が発生してしまい、非効率的です。
そこで、ターミナルとして、輸送連携型倉庫を設置し、荷物を集約してから各納品先へ配送する方式で効率化を目指します。
荷主としては集約を行うことで、リードタイムの削減や在庫効率化などの効果が期待できます。
総合効率化計画認定を受ける
モーダルシフトや輸送網の集約などの効率化事業を推進することは、国が推奨する総合効率化計画認定を受けることにつながります。
自国産業の国際競争力の強化や消費者の需要への対応、環境負荷の低減などの目的で制定された物流総合効率化法によって、国土交通省では物流効率化を支援しています。
この認定によって、事業の立ち上げや実施の補助、輸送連携型倉庫への税制特例、さまざまな金融支援を受けられる可能性があります。
出典:物流総合効率化法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律)の概要|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/common/001476255.pdf
パレットを利用する
手積みによる荷役作業をパレットを利用した形態にするのも一手です。ドライバーにとって、積み込みや荷下ろしの作業は時間もかかり、身体的な負担も大きいです。
パレットやラック、折り畳みコンテナといった輸送機器を導入することで、荷役時間を削減できるでしょう。導入には費用がかかるため、関係者間で費用を分担することを検討してみましょう。
中継輸送をする
中継輸送とは、1人の運転者がすべての行程を行うのではなく、複数人で分担する方法です。ドライバーの身体的な負担を軽減したり、人手不足を解消すると期待されています。
特に、宿泊が必要となる長距離運行はドライバーへの負担が大きいため、労働環境の整備として検討する必要があるでしょう。
ドライバー待機時間を削減する
2024年問題の解決に向けて、ドライバーの荷待ち時間を短縮することも、考えていかなければなりません。
現状ではドライバーの荷待ち時間の平均は1日で、約1時間以上発生しているとされており、1日の拘束時間全体の1割以上を占めているとされています。
荷待ち時間や荷役時間は、荷主の協力なくしては削減できません。パレットの利用など、業務効率化を推進することで、待機時間を削減できるでしょう。
物流業務を平準化する
入出荷量に曜日や月間で波があると、荷待ち時間の発生や積載効率の低下が懸念されます。そのため、貨物の量を平準化することは時間短縮や輸送効率の向上につながります。
荷主としては生産体制の見直しを検討するなど、繫忙期や閑散期をなるべく作らないように検討していくことが大切です。
DX化による業務管理を効率化する
業務管理を効率化する手法として、デジタルツールを利用することが考えられます。勤怠管理や位置情報などをシステム化することで、連絡や確認作業を効率化することができます。
業務管理の効率化は、ドライバーの拘束時間を減らすのに有用であるため、適切な管理を行うことは人員の定着にもつながるでしょう。
配送車両管理をデジタル化する
配送車両の管理をシステム化して管理することも、配送業務の効率化ができます。
例えば、配送ルートをAIによって最適化するなどで、配送時間の短縮や燃料コストの削減といった効果が見込めます。
管理者やドライバーの負担になっている部分をデジタルツールを利用することで、より便利にわかりやすいものにしていきましょう。
運送会社に協力を申し出る
運送業において、取引上、荷主側の方が強い立場にあることが多く、以後の取引を断られることを危惧して適正な交渉ができない環境がありました。
そのため、運送会社と荷主の健全な関係を構築する上でも、荷主側からの協力の申し出が必要になってきます。
運送契約を適正化しておく
荷主が輸送条件を指定する運送契約を適正化しておく必要もあります。運送契約を書面化したり、ドライバーへの賃金を適正に支払う契約を行いましょう。また、近年高騰傾向にある燃料費用について、相談を受けた場合は、速やかな対応が必要です。
正式な契約を結ばずに、無理な働かせ方をしてしまうと、荷主勧告制度や法律違反に該当する恐れがあります。違反しないように、予め内容を確認し、契約を結ぶ必要があります。
出典:物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者が取り組むべき事項
(案) |国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001611954.pdf
荷主が2024年問題で違反した時の罰則内容とは?

労働基準法の規定に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となる可能性があります。協定で定められた時間を超えないように、十分な対策が必須です。
出典:労働基準法 素朴な疑問Q&A|東京労働局
参照:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/hatarakikata_qa_all_191108ok.pdf
荷主も2024年問題の対策をしておこう
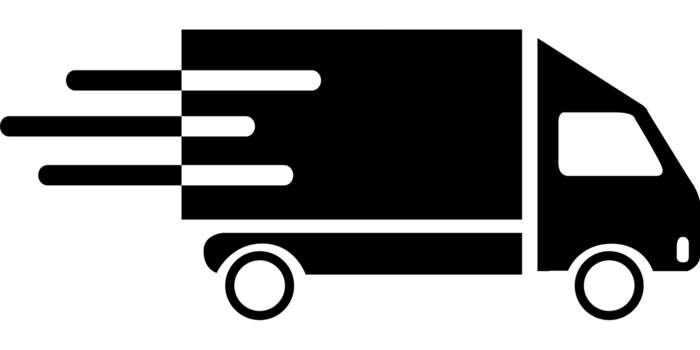
物流業界が、この問題によって受ける影響はかなり大きく、その影響は荷主に対しても大きな課題となっています。物流業界として、この問題に取り組むことは、これからの業務をスムーズに行うためにも必要な事象です。
こういったさまざま課題に対しては、運送会社と荷主の双方の協力なしでは解決が難しいでしょう。持続可能な物流の実現に向けて、できる対策から取り組んでいきましょう。
