運転免許の区分や種類について紹介!取得時期による条件や免許の取得方法についても紹介!
- 物流
車で公道を走るときに必要な自動車運転免許。
2024年7月現在で、自動車運転免許の区分はさまざまで、
免許によって運転できる車両が細かく分類されています。
運転免許の区分や制度・種類を知っておかなければ、
無免許で運転していたといったことになると道路交通法違反となり大変です。
本記事では、運転免許の区分や種類、
取得時期による条件や免許の取得方法について詳しく解説します。
運転免許は3つの区分がある

運転免許の種類には「第一種運転免許」「第二種運転免許」
「仮運転免許」の3つの区分があります。
それぞれどのような免許なのかをみていきましょう。
第一種運転免許
第一種運転免許には「大型免許」「中型免許」「準中型免許」「普通免許」
「大型特殊免許」「大型二輪免許」「小型特殊免許」「原付免許」「けん引免許」が
設定されています。
第一種運転免許は、営利目的ではなく、
基本的には日常生活で車を運転するときに必要な免許です。
第二種運転免許
第二種運転免許には「大型免許」「中型免許」「普通免許」「大型特殊免許」
「けん引免許」が設定されています。
第二種運転免許は、お客様や荷物を運ぶときに代金を徴収し、
営利目的で車を運転するときに必要な免許です。
タクシーやバスでお客様を運ぶ、トラックで荷物を運ぶ際に、
有償で運転する場合には第二種運転免許を所持していなければなりません。
仮運転免許
仮運転免許(仮免許)は、「道路交通法第87条1項」により、
公道で運転の練習をするために必要な免許です。
教習車でなくても「仮免許運転中」の表示し、
免許所有期間が3年以上、
または第二種免許を持っている方を助手席に乗せれば、
仮運転免許をもっている人は行動公道を運転することができます。
運転免許の種類

自動車の運転免許にはさまざまな種類があります(2024年7月現在)。
| 免許証区分 | 運転可能な車両の種類 | |||||
| 大型 | 中型 | 準
中型 |
普通 | 小型
特殊 |
原付
自転車 |
|
| 大型自動車免許
(21歳以上・免許期間3年以上) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中型自動車免許
(20歳以上・免許期間2年以上) |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 準中型自動車免許(18歳以上) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 普通自動車免許 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 原付免許(16歳以上) | × | × | × | × | × | 〇 |
| 小型特殊自動車免許(16歳以上) | × | × | × | × | 〇 | × |
| 大型特殊自動車免許(18歳以上) | 大型
特殊 |
小型特殊 | × | × | 〇 | 〇 |
| 大型自動二輪車免許(18歳以上) | 大型
自動 二輪 |
普通
自動 二輪 |
× | × | 〇 | 〇 |
| 普通自動二輪車免許(16歳以上) | × | 普通
自動 二輪 |
× | × | 〇 | 〇 |
| けん引免許(18歳以上) | 重被
けん引車 |
× | × | × | × | × |
それぞれの免許証の区分の乗車できる人数、積載可能な重さなどは、次でご紹介します。
取得時期によって条件が異なる

上記でご紹介した免許証区分は、
以下のように取得時期によって運転できる車両が異なります。
<平成29年3月12日以降に第一種運転免許を取得>
| 免許の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | 受験資格 |
| 普通免許 | 3.5t未満 | 2.0t未満 | 10人以下 | 18歳以上 |
| 準中型免許 | 7.5t未満 | 4.5t未満 | 10人以下 | 18歳以上 |
| 中型免許 | 11.0t未満 | 6.5t未満 | 29人以下 | ※ |
| 大型免許 | 11.0t以上 | 6.5t未満 | 30人以上 | ※ |
<平成19年6月2日~平成29年3月11日に第一種運転免許を取得>
| 免許の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | 受験資格 |
| 普通免許 | 5.0t未満 | 3.0t未満 | 10人以下 | 18歳以上 |
| 中型免許 | 11.0t未満 | 6.5t未満 | 29人以下 | ※ |
| 大型免許 | 11.0t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 | ※ |
<平成19年6月1日以前に第一種運転免許の取得>
| 免許の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | 受験資格 |
| 準中型(8t)
限定免許 |
8.0t未満 | 5.0t未満 | 10人以下 | 18歳以上 |
表中の※は、特別な教習を修了している場合は
19歳以上かつ普通自動車免許等を1年以上、保有している必要ことが条件です。
準中型免許については、株式会社ジャパン・リリーフの
「準中型免許を取得すると乗れる車の種類とは?4トントラックは運転が可能?」の
記事にて、詳しく紹介されていますので、合わせて参考になさってください。
運転免許の取得方法について
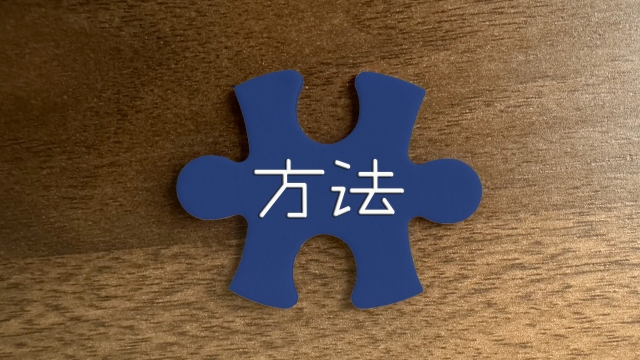
最後に、運転免許を取得するには、どのような方法があるのかご紹介します。
教習所で入所申し込みをする
基本的に運転免許を取得する際は、教習所で指定の技能教習と学科教習を受けます。
教習所は、決められた日時に教習所に通う「通学型」と、
数週間泊まり込みで教習所に通う「合宿免許」があります。
申し込みをする際は、総額費用の確認や、
技能試験に合格しなかった際に再教習で追加料金は必要なのかなど、
教習所によって費用が異なりますので、しっかりと確認を行なってください。
申し込み時は、本人確認書類、印鑑、証明写真、
視力矯正が必要な方は眼鏡やコンタクトなどが必要です。
上記の内容はあくまで基本事項ですので、
入所する予定の教習所の「入所要項」を参考にしましょう。
入所当日
入所当日は、以下が行なわれていることが一般的です。
| オリエンテーリング | 入所説明を受ける |
| 初回学科教習 | 交通法令の遵守・重要性・モラルなどについて学ぶ |
| 適性検査 | 運転能力検査・運転適性検査を受ける |
適性検査の「運転能力検査」では、視力・障がいなど、
運転に必要な身体条件がクリアできているかを検査します。
普通免許を例にあげると、必要な視力は両眼0.7以上かつ片眼0.3以上で、
眼鏡やコンタクトによる矯正は認められています。
もし片目が0.3以下の場合は、もう一方の片目の視力が0.7以上で、
視野が左右150度以上なければいけません。
その他。赤・黄・青などの色彩識別、日常会話、読み書きなど、
運転に支障をきたす項目がないかも検査されるのです。
「運転適性検査」では、自分の性格や癖が
運転にどのような影響をもたらすかを知ることができます。
運転適性検査には合否判定はありませんので、
素直に検査を受けるようにしましょう。
第一段階
第一段階の教習では、学科教習が10時間、
技能教習12時間(MTは15時間)を受けなければなりません。
学科教習は1日に何時間受講しても構いませんが、
技能教習は1日2時間までと決められています。
その理由としては、教習生の疲労のことが考慮されており、
法律で1日2時間と決められているのです。
第一段階の技能教習は、教習所内で教習車を運転します。
学科教習については合否はありませんが、
技能教習は運転技術の基準が満たされなかった場合、
追加教習を受けなければなりません。
追加教習を受ける際は追加料金が必要ですが、
教習所によっては追加教習となった際に
追加料金の上限が設けられているコースを設置しているところもあります。
第一段階は、修了検定(仮免検定)」に合格すると終了です。
第二段階
修了検定に合格すると第二段階の教習へと移行します。
第二段階の教習では、学科教習が16時間、技能教習19時間を受けなければなりません。
学科教習ではAEDを使用した応急処置などを学びます。
技能教習では、仮運転免許を取得していますので、
実際に公道へ出て教習を受けることになります。
狭い教習所内から、走行範囲の広い公道に出ると、
他の車両や歩行者など、さまざまなものに気をつけながら走行しなければなりません。
第二段階の教習をすべて合格し、
最後の「卒業検定」に合格すれば教習所を卒業することになります。
卒業検定は、教習の際に走行した公道を走りますが、
卒業検定のときに走行するコースは
検定当日に発表されるので緊張するかもしれませんが、
技能実習で学んだことを思い出しながら
落ち着いて検定を受けるといいでしょう。
本免学科試験
教習所を卒業後、居住地域管轄の運転免許試験場で学科試験を受けます。
当日は一般に、以下のものを準備しなければなりません。
・仮運転免許
・教習所卒業証明書
・筆記用具
・コンタクトまたは眼鏡
・写真1枚(縦3cm×横2.4cm)※6カ月以内に撮影のもの
・身分証明書(保険証・パスポートなど)
本免学科試験は〇×問題が100問出題され、90点以上が合格であるのが基本です。
試験結果は当日中に発表され、合格していれば運転免許証が発行されます。
まとめ
運転免許の区分や種類、取得時期による条件や免許の取得方法について、
ご理解深まりましたでしょうか。
運転免許の区分について理解しておくことが必須で、
所持していない免許の車両を運転することは道路交通法違反となります。
免許に取得方法についても、流れをご紹介しましたので、熟読なさってください。
本記事を参考に、取得していない免許を取得してみてはいかがでしょうか。
