ライドシェアのメリットとデメリットは?種類や利用できるサービスも解説
- その他
「ライドシェアを利用するメリットって何?」
「ライドシェアを利用するとどんなデメリットがあるの?」
このように、ライドシェアを利用したくてもメリットやデメリットが気になるという人もいるのではないでしょうか。
本記事ではライドシェアとはそもそもどういうものなのか、利用するメリットとデメリット、注意点などについて紹介します。この記事を読むことで、ライドシェアについて詳しくなるだけではなく、メリットやデメリット、注意点を把握した上で利用できるようになるでしょう。
また、ライドシェアの種類や、日本で使えるライドシェアのアプリなどについても紹介しているため、実際にライドシェアを利用するときも参考になるでしょう。
ライドシェアに興味があるけれど詳しく知らない場合や、ライドシェアの利用を検討している場合は、ぜひこちらの記事をチェックしてみてください。
そもそもライドシェアとは
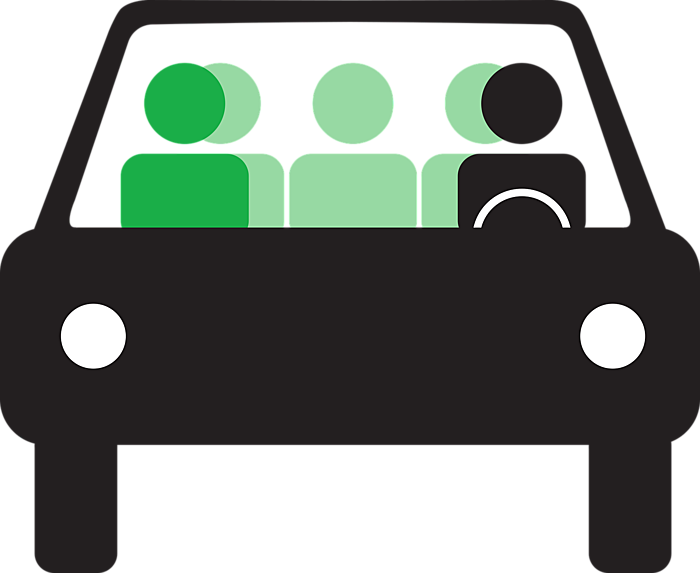
ここからは、ライドシェアはどのようなものなのか紹介していきます。ライドシェアについて知りたい方は、ここからの内容を参考にライドシェアはどんなサービスなのか知っていきましょう。
車の相乗り
ライドシェアの本来の意味は、「Ride(乗る)」と「Share(共有)」で、目的地が同じ人が同じ車に相乗りすることを指します。現在では、アプリを利用してドライバーと利用者をマッチングさせるソーシャルサービスのことを、ライドシェアと呼んでいます。
カーシェアリングとは違う
ライドシェアがドライバーと利用者をマッチングさせるソーシャルサービスなのに対して、カーシェアリングは車を貸し出して共同利用するサービスであるという違いがあります。
ライドシェアでは、車そのものを貸し出すことはなく、車の所有者であるドライバーが運転して、利用者を乗せます。
ライドシェアのメリット

ライドシェアは日本ではまだそれほど普及していませんが、外国では急速に普及してきているソーシャルサービスです。外国でライドシェアの普及が進むのは、ライドシェアにさまざまな魅力的なメリットがあることが理由でしょう。
日本においても、ライドシェアを利用するメリットはいくつもあります。ここからはライドシェアのメリットについて紹介しますので、参考にしてみてください。
- 割り勘で移動コストを節減できる
- アプリと連動した決済で手軽に使える
- 交通空白地帯の有効な交通手段になる
- アプリでドライバーの評価がわかる
- ドライバーは自分の車を有効活用できる
- 同乗により環境にもメリットがある
メリット1:割り勘で移動コストを節減できる
車で移動する場合、車のガソリン代や駐車場代、目的地によっては高速代といった移動コストが発生します。もしライドシェアを利用せず1人で移動した場合は、これらの移動コストは全て自分で支払わなければなりません。
ライドシェアを利用して同じ目的地に向かう利用者(同乗者)を募れば、ドライバーと利用者の全員で移動コストを割り勘できるため、移動コストを節減できるのです。
また、タクシーを利用するよりも費用が安いというメリットもあります。ライドシェアはドライバーも利用者も、どちらも移動コストを節減できる移動手段です。
メリット2:アプリと連動した決済で手軽に使える
ライドシェアアプリを利用した場合、支払い方法はアプリと連携した決済で行えるため、手軽に済ませることができます。
あらかじめ利用する専用のアプリに自分のクレジットカード情報を登録しておく必要がありますが、登録さえしておけばキャッシュレスで決済が利用可能です。また、料金も事前にアプリで確認できるため、安心です。
メリット3:交通空白地帯の有効な交通手段になる
交通空白地帯とは、電車の駅やバス停などが一定の距離にない地域のことです。日本には過疎化して交通空白地帯になった地域が多いですが、ライドシェアがあることで、地域の有効な交通手段になるでしょう。
すでにライドシェアを導入している兵庫県養父市の山間部エリアでは、国家戦略特区の制度を利用したライドシェアが行われています。タクシーやバスを導入することのできない地域にとって、ライドシェアは新たな交通手段になるでしょう。
出典:自家用有償観光旅客等運送事業「やぶくる」の取り組みについて|特定非営利活動法人養父市マイカー運送ネットワーク
参照:https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/soukou-magazine/1908-5sougoukoutsu.pdf
メリット4:アプリでドライバーの評価がわかる
ライドシェアのアプリでは、ドライバーの評価を確認できるため、嫌なドライバーにあたる可能性を低くできることもメリットでしょう。
ライドシェアではまったく知らない人と相乗りすることになるため、不安を抱く人も多いでしょう。しかしアプリでライドシェアの利用者からの評価が公表されているため、乗る前にどんなドライバーなのか知ることができ、嫌な思いをする可能性は低くなるでしょう。
メリット5:ドライバーは自分の車を有効活用できる
自家用車を保有していても、乗るのは休日のみという人もいるでしょう。車に乗る機会が少なければ、維持費ばかりがかかってしまうこともあります。
しかしライドシェアをすれば、すでにある車を使って手軽に働くことが可能です。車の維持コストを節減することも可能でしょう。
メリット6:同乗により環境にもメリットがある
車で移動すると移動距離に応じてCO2を排出してしまうため、車が環境に与える影響は大きいです。しかしライドシェアをした場合、一緒に移動できる人数が増えるため、環境への負荷を軽減できるでしょう。
また、1つの車に複数の人が乗ることで交通量を減らし、交通渋滞を緩和できるというメリットもあります。
ライドシェアのデメリットと注意点

ライドシェアにはさまざまなメリットがありますが、デメリットや注意点もあります。
ライドシェアは利用者にとってドライバーの質や信頼性が不確かであるため、ドライバーによる事故や犯罪への注意が必要です。
また、ドライバー側も利用しているプラットフォームのサービスが停止した際の補償がないため、失職してしまうといったデメリットがあります。
ライドシェアの代表的な種類・方式

一言でライドシェアといっても、いくつか種類があります。ここでは、ライドシェアの種類を5つ紹介するため、ライドシェアにはどのような種類があるのか知っておきましょう。
カープール型
「カープール型」のライドシェアは、出発地・目的地が同じ利用者を自家用車に乗せる相乗り型のライドシェアです。
通勤ラッシュ時の道路の混雑を避けるために、アメリカでよく利用されているライドシェアで、主要交通手段の1つにもなっているほど普及しています。
カジュアルカープール型
「カジュアルカープール型」は、面識はないが目的地が同じ他人を同乗させる方式のライドシェアです。
通勤中のドライバーが、専用乗り場に並んでいる目的地が同じ人を自分の車に同乗させ、目的地まで一緒に移動する形で、基本的にドライバーと利用者に面識はありません。
バンプール型
「バンプール型」は、大型のバンを利用して、多人数が同乗して移動できるようになっているライドシェアのことです。ライドシェアの中でも、使う車が大型車両のバンであればバンプール型になります。
バンプール型は通学や通勤で使われており、一般的にはドライバーと利用者が費用を負担する形になっています。中には、行政や企業から補助で費用が軽減されるケースもあります。
TNCサービス型
「TNCサービス型」は近年発展しているサービスで、サービス提供会社(プラットフォーム)が一般ドライバーと、相乗りしたい利用者の仲介をするものです。
TNCサービス型の予約は携帯アプリで行い、乗車後に定められた料金を支払う形になっています。リアルタイムライドシェアリングやオンデマンドライドシェアリング、ライドソーシングと呼ばれる場合もあります。
タクシー相乗り型
「タクシー相乗り型」は、2021年11月から開始されたタクシー相乗りサービスによるライドシェアのことです。タクシー相乗り型ではスマートフォンのアプリで近い目的地の利用者をマッチングして、料金は利用者が乗車距離に応じて割り勘で支払う形になっています。
ここまで紹介してきたカープール型やバンプール型、TNCサービス型はアメリカでのライドシェアでしたが、タクシー相乗り型は国土交通省が認めた新たな日本の制度です。
出典:新たにタクシーの「相乗りサービス」制度を導入します!|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000338.html
ライドシェアの普及状況

ライドシェアは海外で急速に普及していますが、日本ではあまり普及してきていません。これは、道路運送法の第七十八条により、自家用車による有償運送、いわゆる白タク行為が原則禁止とされていることが影響しているでしょう。
しかし近年では、交通空白地帯での自家用有償運送や、国家戦略特区法による訪日外国人観光客を対象とした自家用有償運送が行われるなど、制度の改正が少しずつ進んでいます。
出典:道路運送法|e-Gov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000183
出典:国家戦略特区法の一部改正法概要(自家用有償運送等の比較)|国土交通省
参照:https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc_wg/h29/shouchou/20170929_shiryou_s_1.pdf
日本で使えるライドシェアの主なアプリ

ここからは、日本でも利用できる主なライドシェアアプリを4つ紹介します。
まだ日本ではライドシェアが普及していないことや規制の影響などから、タクシー相乗り型が主流となっています。ここで紹介しているアプリもタクシー相乗り型が多いため、その点に注意して利用してみましょう。
出典:長距離ライドシェア(相乗り)|notteco(のってこ!)
参照:https://notteco.jp/info/legal
出典:service|Geecoo, Inc.
参照:https://geecoo.co.jp/
出典:株式会社NearMe|会社情報
参照:https://nearme.jp/about/
出典:企業情報|WILLER TRAVEL【公式】
参照:https://travel.willer.co.jp/company/
| アプリ名 | 対象地域 | 支払方法 |
|---|---|---|
| notteco | 全国 | 当日現金決済 |
| AINORY | 日本国内 | 最後に降りるメンバーに支払う |
| NearMe Town | 東京都中央区、千代田区、港区、江東区全域 | クレジットカード支払い |
| mobi | 根室市、大館市、豊島区、名古屋市、羽鳥市などの一部地域 | クレジットカード、銀行振込、現金 |
notteco(のってこ!)
「notteco(のってこ!)」は目的地が近い人を対象にライドシェアできるアプリで、移動する人がいれば全国で利用できます。タクシー相乗りではなく、カープール型のライドシェアです。
ドライバーの評価や車種、車内での注意事項の他に、ドライバーの性別・年齢についても公開されているため、安心して利用できるでしょう。
出典:長距離ライドシェア(相乗り)|notteco(のってこ!)
参照:https://notteco.jp/info/legal
AINORY
「AINORY」はタクシー相乗り型のライドシェアができるアプリで、対象地域は日本国内限定です。
1か月先まで出発地から目的地までの相乗りを募集できるため、相乗りしてくれる人をしっかり探せるでしょう。相乗り希望者がいれば、乗車経路や運賃などから条件のよい人を承認して相乗り成立となります。
AINORYではアプリ決済ではなく、最後に降りる人に支払う方式です。料金はあらかじめ用意しておきましょう。
出典:service|Geecoo, Inc.
参照:https://geecoo.co.jp/
NearMe Town(ニアミータウン)
「NearMe Town(ニアミータウン)」は最大5人まで相乗り可能なシャトルの相乗りサービスで、同乗者がいた場合には最大50%お得になるサービスです。
通勤や子どもの送迎などの定期的な利用や、週末の家族の移動などでも利用できます。ただ、利用可能エリアは東京都中央区、千代田区、港区、江東区と少ないです。
出典:株式会社NearMe|会社情報
参照:https://nearme.jp/about/
mobi(モビ)
「mobi(モビ)」は、エリア内であれば30日間定額で相乗りできるサービスです。出発地と目的地をリクエストするだけでいつでも迎えが来て、目的地まで送ってくれます。
対象エリアは、北海道から四国までの一部市町村内のエリアとなっているため、どこでも使えるという訳ではありません。
支払いはクレジットカードで行いますが、乗り放題プランの場合は銀行振込、ワンタイムプランは現金での支払いも可能です。
出典:企業情報|WILLER TRAVEL【公式】
参照:https://travel.willer.co.jp/company/
ライドシェアはメリットも多く普及が期待される新たな交通手段

ライドシェアは海外では普及していますが、さまざまな理由で日本ではまだ普及していない交通手段です。
ライドシェアには移動コストの節減や車の有効活用、環境への配慮など多くのメリットがあるため、今後はさらに普及し活用されていくことが期待されています。
ぜひこの記事を参考に、ライドシェアの活用について検討してみてください。
