3級自動車整備士合格への道!取得条件や取得方法、過去問についても徹底解説!
- その他
自動車整備士の資格の中で、基本となるのが3級自動車整備士です。
自動車の基本的な整備を行なう上で、3級自動車整備士の資格を欠かせません。
本記事では、3級自動車整備士の取得条件や取得方法、過去問について、
詳しく解説します。
自動車整備士の3級でできる仕事内容は?

3級自動車整備士は、オイル交換、タイヤ交換、点検整備など、
基本的な作業を行なうことができる資格です。
3級自動車整備士は、自動車の「走る」「曲がる」「止まる」の
保安基準に関わる部分の分解・整備を行なうことができません。
これらの業務を行なうためには、2級・1級自動車整備士の資格が必要となります。
自動車整備士の資格の種類については、株式会社ジャパン・リリーフの
「自動車整備士の資格の種類や違いを徹底解説!受験方法や費用、合格率についても紹介!」の記事も役に立ちますので、
合わせて参考になさってください。
3級自動車整備士の資格を取得する条件

3級自動車整備士の資格を取得する条件は、以下の通りです。
自動車整備系の高校、専門学校を卒業の場合(3級整備士課程)
自動車整備系の高校、専門学校を卒業(3級整備士課程)した場合、
卒業時に3級自動車整備士の資格が取得可能です。
教育機関で専門的なことを学ぶことができるため、実務経験が必要ないのです。
機械工学科等卒業の場合(大学、専門、高校、または職業訓練など)
機械工学科等卒業の場合(大学、専門、高校、または職業訓練など)は、
0.5年以上の実務経験をしておく必要があります。
実務経験が認められる認定工場などで、経験を積みましょう。
上記以外を卒業
上記以外を卒業した場合は、1年以上の実務経験を積まなければなりません。
上記と同様に、実務経験は原則、認証工場や指定工場でなければなりません。
3級自動車整備士の資格取得の方法と流れ

自動車整備士の資格の受験方法と流れについてみていきましょう。
都道府県の自動車整備振興会で申請手続きを行なう
受験申請は、国土交通省か自動車整備振興会で行ないます。
自動車整備士の資格を取得するには、
国土交通省が行なっている検定試験に国土交通大臣の認可が下りている機関で
自動車整備技能登録試験(登録試験)の合格する必要があります。
登録試験は、試験合格後に国土交通省に免除申請すると、
検定試験に合格した扱いとなるのです。
学科試験・実技試験を受験する
次に、学科試験・実技試験を受験します。
学科試験・実技試験の内容は以下の通りです。
| 学科試験 | 自動車の構造・機能、工具の構造・使用方法、点検・修理・調整、完成検査の方法、保安基準など |
| 実技試験 | 実際の自動車部品を使用した点検・分解・組立て・調整、完成検査、整備用の試験機や計量器をはじめとした工具の取扱いを実践 |
合格証明書発行の手続きを行なう
受験合格後は、各都道府県の自動車整備振興会で手続きを行ないます。
手続きに必要なものは、自動車整備振興会によるため、
事前に問い合わせて確認してください。
合格証明書を受け取ることができれば、自動車整備士として活躍することが可能です。
3級自動車整備士の資格の難易度
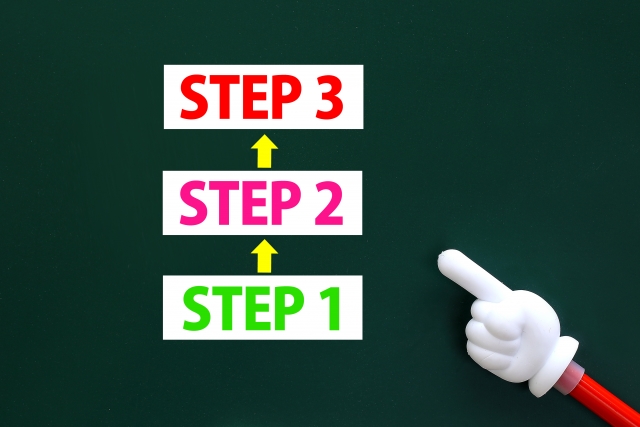
3級自動車整備士は、筆記・実技ともに合格率は60%~80%程度となっています。
とくに学科試験は、運転免許の学科試験と比べても合格率は高いといえるでしょう。
合格率が高いといえども、日本自動車整備振興会連合会の過去問を中心に学習し、
市販のテキストを利用して自動車の知識を身につけなければなりません。
また実技に関しては、自動車整備工場で資格者に指導を受けると上達します。
3級自動車整備士が2級自動車整備士になるためには?

3級自動車整備士の資格を持っていたとしても、
すぐに2級国家資格を受けることはできません。
3級自動車整備士を取得後、まず3年間の実務経験が必要です。
大学・高専の機械工学科を卒業している場合は、
3級自動車整備士の資格を取得後、実務経験が1年6ヶ月以上必要となります。
2級自動車整備士課程を学べる自動車整備系の専門学校・大学を卒業している場合は、
実務経験は必要ありません。
これらの条件を満たした上で、国家資格に合格すると、
2級自動車整備士になることができます。
3級自動車整備士の過去問を紹介!
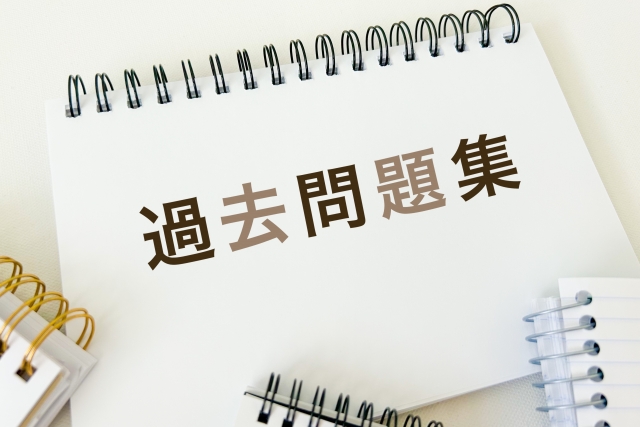
3級自動車整備士「二級ガソリン自動車」の過去問についてみていきましょう。
以下の学科試験・実技試験の一例は、
令和6年度第1回自動車整備技能登録試験の一部(改変)です。
学科試験
まずは、学科試験からご紹介します。
[問題]
ピストン・リングに関する記述として、適当なものは次のうちどれか。
(1)スカッフ現象は、ピストン・リングの拡張力が小さいほど、ピストン・リング幅が厚
いほど、またピストン速度が速いほど起こりやすい。
(2)スティック現象とは、カーボンやスラッジ(燃焼生成物)が固まってリングが動かなく
なることをいう。
(3)アンダ・カット型のコンプレッション・リングは、外周下面がカットされた形状にな
っており、一般にトップ・リングに用いられている。
(4)テーパ・フェイス型は、しゅう動画が円弧状になっており、初期なじみの際の異常摩
耗が少ない。
この問題の解答は「(2)」です。
上記のほか、中学校の理科で学習する電気回路や、
オームの法則の問題などが出題されています。
実技試験
続いて、実技試験をご紹介します。
◎台上にあるリレーを使用したランプ点灯回路について、次の各問いに答えなさい。な
お、必要事項は、台上の留意事項に示してあります。測定は、台上にある測定機器を用
いて行ないなさい。
[問1]
ランプ点灯回路のスイッチをONにしたときの、バルブの点灯状態を確認し、結果について次の3つの中から一つ選んで、解答欄に番号を記入しなさい。
[問2]
ランプ点灯回路のスイッチを操作したときの、①~⑬の各測定端子と測定端子⑭間の電圧を測定し、測定値を下表の該当欄に小数点以下第1位(小数点以下第2位を切り捨て)まで記入しなさい。
このように実践的な問題が出題されているのです。
3級自動車整備士の資格保持者の体験談3つ

3級自動車整備士の資格保持者の体験談についてみていきましょう。
~体験談①~Mさん・20代・保持歴2年
10代で普通免許を取得し、自分の車を整備することが好きになりました。
好きなことを仕事にするために、3級整備士の資格を取って、
現在では自動車工場で働いています。
基本的な車の整備ができることは自分のためだけでなく、
お客様のためにもなっていることが嬉しく思います。
~体験談②~Nさん・20代・保持歴3年
3級自動車整備士の資格では、車の扱える範囲が限られていることから、
2級自動車整備士の資格取得をめざすようになりました。
実務経験を積んでいる間も、
2級自動車整備士の資格を取ろうという気持ちが強くなりました。
現在、過去問などを扱いながら、
2級自動車整備士の資格取得をめざして努力しています。
~体験談③~Yさん・20代・保持歴1年
3級自動車整備士の資格は、オイル交換やタイヤ交換など、
基本的な整備を行なうことができます。
作業自体はそれほど難しいものではありませんが、
車を走らせる上で重要な部分を担っていると思っています。
毎日やりがいを感じながら仕事をしています。
まとめ
3級自動車整備士の取得条件や取得方法、過去問について、
ご理解深まりましたでしょうか。
自動車整備士として働くためには、まず3級自動車整備士の資格を取得しましょう。
3級自動車整備士の仕事は、基本的な車の整備が中心となりますが、
上級の自動車整備士の資格をとるためにも必要な資格です。
また、3級自動車整備士の資格を取得する際の過去問についてもご紹介しましたので
ぜひチャレンジしてみてください。
本記事を参考に、
あなたも3級自動車整備士の資格の取得を目指してみてはいかがでしょうか。
