トラックの白ナンバーと緑ナンバーの違いを徹底解説│必要な許可や免許、書類についても紹介
- トラックドライバー
トラックに装着されているナンバープレートには、
白ナンバーのものと緑ナンバーのものがあります。
同じトラックの車種であっても、
白ナンバーと緑ナンバーそれぞれを装着している場合があります。
白ナンバーと緑ナンバーの違いには、どのようなものがあるのでしょうか。
本記事では、トラックの白ナンバーと緑ナンバーの違い、
必要な許可や免許、書類について、詳しく解説します。
トラックの白ナンバーと緑ナンバーの違いとは
白ナンバーのトラックは自家用トラック、緑ナンバーのトラックは営業用トラックと区分されています。自家用トラックは自社の荷物を自社の車で運ぶトラックであるのに対し、営業用トラックはお客様の荷物を有償で運ぶトラックです。
トラックの用途によってナンバープレートの色で区別されており、白ナンバーと緑ナンバーでは運搬物の違いや、税金、保険料などの維持費が異なります。
また、緑ナンバーのトラックを運用する事業所においては、飲酒運転防止のために運転前後にアルコールチェックをすることが義務化されています。
出典:自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について |国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03alcohol/index.html
運搬物の違い
緑ナンバーのトラックでは、営利目的で他人の物を運ぶことができます。これが白ナンバーと緑ナンバーの大きな違いです。
緑ナンバーのトラックの運搬物は多岐に渡ります。生活に身近な物では、宅配便などの運送業の配達車、引越し業者の運搬車などです。これらのトラックは荷主から依頼され、荷物を預かり、指定場所に荷を運び、運賃(報酬)を受け取る業務に使用されています。
一方、白ナンバーのトラックは自分や家族の引越し荷物の運搬、工事業者が自社の道工具や仕事で使用する資材を運搬するなど、営利目的のない自社や自分の荷物を運ぶ目的でのみ使用可能です。
そのため、白ナンバーのトラックを業務用のトラックとして運送業などに使用すると違法になります。
出典:貨物自動車運送事業法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000083
税金の違い
白ナンバーと緑ナンバーでは、緑ナンバーの方が税金は安くなります。
乗用車の自動車税は総排気量で分類されていますが、トラックの自動車税は最大積載量によって分類され、自動車重量税は車両総重量で分類されています。どちらも白ナンバーより緑ナンバーの方が金額設定は安いです。
自動車税
最大積載量が8トンを超えるものにあっては、最大積載量7トン超~8トン以下であるものに適用される税額に、最大積載量が8トンを超える部分1トンごとに、白ナンバー車は6,300円、緑ナンバー車は4,700円を加算した額となります。
下記の自動車税額は2022年9月に確認した金額であり、今後変更になる可能性があります。
出典:自動車税種別割|東京都主税局
参照:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/car_shubetsu.html#j_7
| 最大積載量 | 白ナンバー | 緑ナンバー |
|---|---|---|
| 1トン以下 | 8,000円 | 6,500円 |
| 1トン超~2トン以下 | 11,500円 | 9,000円 |
| 2トン超~3トン以下 | 16,000円 | 12,000円 |
| 3トン超~4トン以下 | 20,500円 | 15,000円 |
| 4トン超~5トン以下 | 25,500円 | 18,500円 |
| 5トン超~6トン以下 | 30,000円 | 22,000円 |
| 6トン超~7トン以下 | 35,000円 | 25,500円 |
| 7トン超~8トン以下 | 40,500円 | 29,500円 |
自動車重量税
下記の自動車重量税は、エコカー以外の車両の基準額を記載しています。エコカー減税対象車、及び登録から13年以上経過した車両の自動車重量税は、下記の表と異なります。
また、下記の自動車重量税は2022年9月に確認した金額であり、今後変更となる可能性があります。
出典:令和3年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(フローチャート) その2|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/common/001403201.pdf
| 車両総重量 | 白ナンバー | 緑ナンバー |
|---|---|---|
| 1トン以下 | 3,300円 | 2,600円 |
| 1トン超~2トン以下 | 6,600円 | 5,200円 |
| 2トン超~2.5トン以下 | 9,900円 | 7,800円 |
| 2.5トン超~3トン以下 | 12,300円 | 7,800円 |
| 3トン超~4トン以下 | 16,400円 | 10,400円 |
| 4トン超~5トン以下 | 20,500円 | 13,000円 |
| 5トン超~6トン以下 | 24,600円 | 15,600円 |
| 6トン超~7トン以下 | 28,700円 | 18,200円 |
| 7トン超~8トン以下 | 32,800円 | 20,800円 |
点検整備にかかる費用の違い
自動車は、認定工場で点検整備をするルールがあります。それはトラックも同様であり、白ナンバートラックは22項目、緑ナンバートラックは50項目の点検整備を受ける必要があります。
当然、点検項目が多い分、緑ナンバートラックの方が点検整備費用は高額です。
出典:自動車の点検整備|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/tenken/t1/t1-2/
点検期間
点検期間は下記の通りです。ただし、8トン未満のトラックは、車検の有効期間が初回のみ2年間となるため、12ヵ月目の点検は定期点検整備を実施します。
白ナンバーと緑ナンバーを比べると、緑ナンバーの方が点検項目と頻度が多くなっています。業務用に使用する緑ナンバー車は白ナンバー車と比べ、走行距離や使用頻度が多いため、点検期間の間隔が短くなっているのです。
出典:自動車の点検整備|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/tenken/t1/t1-2/
出典:国土交通省提出資料|内閣府
参照:https://www8.cao.go.jp/kisei/giji/03/wg/action/12/2-2-1.pdf
| 点検期間 | 白ナンバー | 緑ナンバー |
|---|---|---|
| 定期点検整備 | 6ヵ月ごとに22項目 | 3ヵ月ごとに50項目 |
| 法定点検(車検) | 12ヵ月ごとに83項目 | 12ヵ月ごとに100項目 |
自動車保険(任意)の保険料の違い
白ナンバー車と緑ナンバー車では、緑ナンバー車の方が保険料は高額になります。また、緑ナンバー車の任意保険を引き受けてくれる保険会社は少なく、普通車でよく利用されるネット自動車保険ではほとんど引き受けてもらえません。
白ナンバー・緑ナンバーにそれぞれ必要な許可

白ナンバー・緑ナンバーにそれぞれ必要な許可は、以下の通りです。
| 白ナンバー | 緑ナンバー | |
| 国土交通大臣または
地方運輸局長の許可 |
不要 | 必要 |
緑ナンバーは、営業用車両であることを示すもので、
運送業者がお客様から有償で荷物や人を輸送する際に、
車両に装着しなければなりません。
白ナンバーで有償運送を行なった場合、罰則が科せられる可能性があります。
白ナンバー・緑ナンバーの運転に必要な免許

白ナンバー・緑ナンバーの運転に必要な免許は、以下の通りです。
| 白ナンバー | 緑ナンバー | |
| 第二種免許 | 不要 | 必要 |
緑ナンバーを装着している車両を、有償で人や物を輸送する際に運転する場合は、
第二種免許が必要となります。
普通免許、中型免許、大型免許それぞれに第二種免許の設定がありますので、
運転する車両の大きさに応じて、第二種免許を取得しなければなりません。
白ナンバー・緑ナンバーを取得する方法と流れ・必要書類
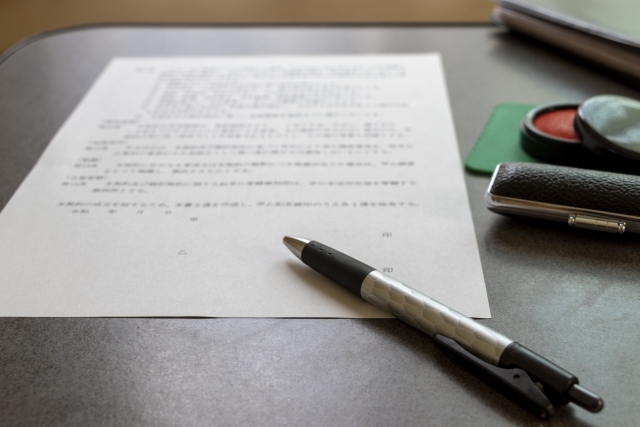
白ナンバー・緑ナンバーを取得する方法と流れ・必要書類についてみていきましょう。
白ナンバーの場合
まず、白ナンバーを取得する際の方法と流れ・必要書類についてご紹介します。
必要書類
白ナンバーを取得する際は、以下の書類が必要です。
| 必要書類 | 内容 | |
| 1 | 自動車検査証(車検証) | 車の所有者や車両情報を確認するための書類 |
| 2 | 申請書(第3号様式) | 運輸支局の窓口で入手するか、国土交通省のウェブサイトからダウンロード |
| 3 | 手数料納付書 | 自動車検査登録印紙や自動車登録印紙を貼付けて提出 |
| 4 | 自動車税申告書 | 運輸支局にある自動車税事務所で入手 |
| 5 | ナンバープレート | 現在のナンバープレートを返納 |
| 6 | 希望番号予約済証 | 希望ナンバーを申し込んだ場合に必要 |
上記以外に、場合によっては、車庫証明書や、住民票が必要となります。
また、代理人が白ナンバープレートを申請する際は、委任状が必要です。
取得する方法と流れ
白ナンバーを取得する方法と流れは、以下のようになっています。
| 必要書類 | 内容 | |
| 1 | 必要書類の準備 | 前述の必要書類を用意する |
| 2 | 運輸支局で手続き | 必要書類をもって運輸支局で書類を提出する |
| 3 | ナンバープレート交付 | 登録手続き完了後、白ナンバーの交付を受ける |
基本的に車両へのナンバープレートの取り付けは自身で行ない、
車両後部に取り付けるナンバープレートには、
運輸支局の職員が封印を取り付けてくれます。
緑ナンバーの場合
続いて、緑ナンバーを取得する際の方法と流れ・必要書類についてご紹介します。
必要書類
緑ナンバーを取得する際は、以下の書類が必要です。
| 必要書類 | 内容 | |
| 1 | 自動車検査証(車検証) | 車の所有者や車両情報を確認するための書類 |
| 2 | 手数料納付書 | 自動車検査登録印紙や自動車登録印紙を貼付けて提出 |
| 3 | 事業用自動車等連絡書 | 運輸支局で発行される書類で、車庫証明の代わりとなる |
| 4 | 申請書 | 運輸支局で入手 |
上記以外に、個人事業主の場合は住民票、
法人の場合は、履歴事項全部証明書が必要となります。
取得する方法と流れ
緑ナンバーを取得する方法と流れは、以下の通りです。
| 流れ | 内容 | |
| 1 | 運送業許可の
取得条件を満たす |
・申請する事業の種類の決定
・資金、事務所などを確保する |
| 2 | 必要書類準備・作成 | ・一般貨物自動車運送事業許可申請書や添付書類を準備
する |
| 3 | 運輸支局への申請 | ・運輸支局へ必要書類を提出する |
| 4 | 法令試験の受験 | ・役員(または個人事業主)が法令試験を受験、合格する |
| 5 | 審査結果の確認 | ・運輸支局で審査に合格すると、許可証が交付される |
| 6 | 登録免許税の納付と
選任届の提出 |
・登録免許税を納付
・運行管理者と整備管理者を選任 |
| 7 | 許可書交付式と
車両の変更 |
・運輸支局での許可書交付式で許可証の受け取り
・車検証を事業用(緑ナンバー)に書き換え ・運輸開始前確認を行い、事業用自動車等連絡書を取得 ・車両に緑ナンバーを取り付け |
| 8 | 運輸開始届の提出 | ・運輸開始届を運輸局に提出する |
白ナンバーと比較すると、ナンバープレートを取得するまでの段階が多いですので、
一段階ずつクリアしていきましょう。
緑ナンバーを取得する利点

緑ナンバーを取得する利点は、運送事業として報酬を得る業務ができることです。
白ナンバーのトラックでは自社の荷物や商品の運搬など、自社のサービスに帰属し運搬によって報酬を得ないという原則がありますが、緑ナンバーのトラックでは他者の荷物を有償で運べます。
他にも、以下のような利点があります。
社会的信用が高い
そもそも、国から運送業の許可を得た事業者でないと、緑ナンバーを取得することはできません。
運送業の許可を得るためには、法令試験の受験、運輸局での審査をクリアしなくてはならず、これらをクリアした事業者であるという事実が、取引先や金融機関からの社会的信用に繋がります。
出典:トラック事業を始めるには|関東運輸局
参照:https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/kamotu/kamotu_jigyoukaisi/index.html
従業員へ社会的安心を提供できる
運送業の許可を得るための条件として、従業員の社会保険の加入義務があります。
運送業の許可を得る際に、社会保険の加入状況の他にも資金状況や事業計画の確認が行われているため、運送業の許可を得ている企業であれば、会社の経営状況を国が認めたという社会的安心を得ることができます。
出典:一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について|関東運輸局
参照:https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/kamotu/kamotu_jigyoukaisi/date/syorihousin_191101.pdf
税制面で白ナンバーよりも優遇されている
車両総重量は5トン以下、最大積載量は2トン超~3トン以下のトラックの場合、自動車重量税は、白ナンバ―車の20,500円に対し、緑ナンバー車は13,000円です。また、自動車税は白ナンバー車の16,000円に対し、緑ナンバー車は12,000円となっています。
合計すると、白ナンバー車の税金が36,500円に対して、緑ナンバー車の税金は25,000円となり、その差は11,500円です。つまり、緑ナンバーの税金は白ナンバーの約2/3と優遇されています。
出典:東京都主税局|税金の種類|自動車税種別割|7税率(年額)
参照:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/car_shubetsu.html#j_7
出典:国土交通省|ホーム>政策・仕事>自動車>自動車重量税額について|フローチャート・税額表|継続車検を受ける場合
参照:https://www.mlit.go.jp/common/001403201.pdf
緑ナンバーを取得する欠点
緑ナンバーを取得する欠点は、運送業の届け出をするための準備などに数ヵ月かかることです。
運送業の届け出のためには事業所に5台以上の車両を保有することや、事業所の立地、資金面の確保、運行管理者の設置など様々な条件があります。これらの条件をクリアし、陸運局の審査を受け無事に審査通過しなければ、緑ナンバーを取得することはできません。
緑ナンバーの取得には時間がかかるという欠点の他にも、自賠責保険や任意自動車保険が高額になるという欠点もあります。
出典:貨物自動車運送事業法ハンドブック|公益社団法人 全日本トラック協会
参照:https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/publication/jigyoho_handbook.pdf
任意自動車保険が大変
車両保険には、加入義務のある自賠責保険と任意加入の任意自動車保険があります。
自賠責保険は車両登録の際や車検の際に、加入、更新を行う保険です。一方、任意自動車保険に加入義務はありませんが、トラックの事故では車両の大きさ、重量などから重大な事故になることが少なくないため、任意自動車保険に加入することをおすすめします。
保険料が白ナンバーと比べ割高
契約条件や保険会社で異なりますが、緑ナンバー車の任意自動車保険は白ナンバー車の約1.5倍~2倍と言われています。
ただ、死亡事故などの重大な損害を与えた場合など、多額の賠償金を支払う場合も想定して、任意自動車保険に加入しておきましょう。
緑ナンバーを引き受けてくれる保険会社は限られる
緑ナンバー車の任意保険を取り扱っている保険会社は少ないと言われており、ネット自動車保険ではほとんど取り扱いがありません。
大手の自動車保険会社で取り扱われている他、全国トラック交通共済協同組合連合会の各支部で自動車共済が取り扱われています。
白ナンバー・緑ナンバーの車両の規則と制限

白ナンバー・緑ナンバーの車両の規則と制限についてご紹介します。
トラック整備の基本的な整備については、
株式会社ジャパン・リリーフの「トラック整備の基本的な知識とは?各点検内容と日常点検に使う工具を紹介」の記事も役に立ちますので、
合わせて参考になさってください。
定期点検と整備の規定
白ナンバーと緑ナンバーの定期点検と整備の規定は、以下のようになっています。
| 白ナンバー | 緑ナンバー | |
| 日常点検 | 義務ではない | 運行開始前に必須 |
| 定期点検 | 1年ごとの点検(義務ではない) | 3カ月に1回以上の点検必須 |
| 車検 | 2年に1回 | 1年に1回 |
有償で人やものを運ぶ緑ナンバーでは、
より安全に業務を行なうために、点検・整備の規定が厳しいです。
車検・保険の必要条件
車検についても、
以下のように緑ナンバーのほうが短期間で車検を受けなければなりません。
| 白ナンバー | 緑ナンバー | |
| 車検 | 2年に1回 | 1年に1回 |
また、加入必須の保険は、以下の通りです。
| 白ナンバー | 緑ナンバー | |
| 加入必須の
保険 |
・自賠責保険 | ・自賠責保険 ・任意保険
・貨物賠償責任保険 |
やはり、緑ナンバーのほうが加入必須の保険が多いことがわかります。
運賃の規定と計画書の提出
緑ナンバーの場合は、事業を開始する前に、
国土交通大臣に、運賃規定の計画書を提出しなければなりません。
有償で人やものを運ぶ以上、これらの申請を規定通りに進める必要があります。
白ナンバーの場合は、これらの書類の提出は必要ありません。
運転時間と休憩時間の規制
白ナンバーの場合は、運転時間と休憩時間の規制はありませんが、
緑ナンバーの場合は、以下のような規制が採られています。
| 項目 | 内容 | |
| 1 | 連続運転時間 | 4時間を超えての連続運転は不可 |
| 2 | 休憩時間 | 4時間の運転で、30分以上の休憩が必要 |
| 3 | 休憩分割 | 30分の休憩が一度に取れない場合、10分以上の休憩を複数回に分けて、合計30分以上でも可能 |
| 4 | 休憩場所確保 | サービスエリアやパーキングエリアなどが満車で休憩できない場合、4時間30分まで連続運転時間が延長される場合あり |
| 5 | 運転中断 | 休憩時間は原則として運転中断となり、荷積み・荷下ろしなどの作業時間は含まれない |
休憩時間は原則として運転中断となり、荷積み・荷下ろしなどの作業時間は含まれない
第二種免許運転者の過労運転を防ぐために、これらの規制が設けられているのです。
安全運転義務と指導
白ナンバー・緑ナンバーに関係なく、
道路交通法や道路運送法を遵守しなければなりません。
とくに、道路交通法の安全運転義務違反に触れないように、
安全な運転操作、適切な条件判断を行なう必要があります。
まとめ

トラックの白ナンバーと緑ナンバーの違い、
必要な許可や免許、書類について、ご理解深まりましたでしょうか。
緑ナンバーが装着されている車は、営業車として利用されています。
緑ナンバーの車両は、点検や保険の条件が、白ナンバーよりも厳しいのは、
有償で人やものを運ぶことが背景にありました。
緑ナンバーの車両を保有する際は、
白ナンバー車両の保有とは手続きが異なりますので、
この記事で手続き内容を確認してください。
本記事を参考に、白ナンバーと緑ナンバーの違いについて知っていただければ幸いです。


